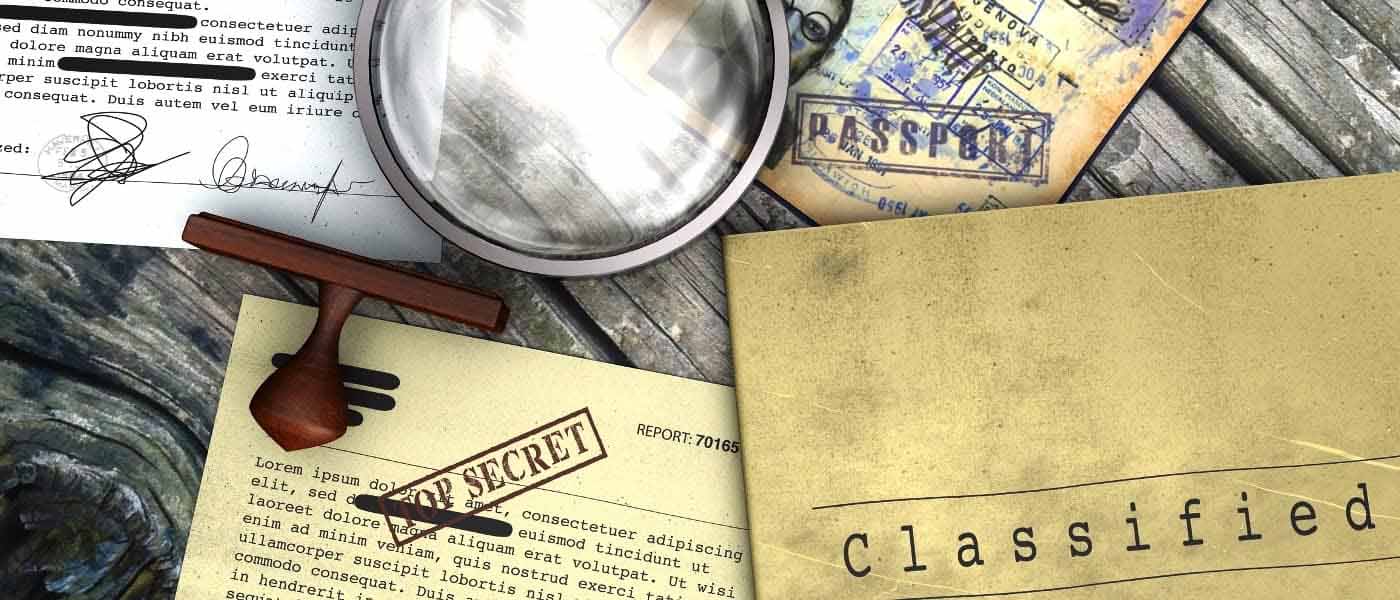Post-War Europe: Refugees, Exile and Resettlement, 1945-1950
本コレクションはロンドンのウィーナー・ホロコースト図書館および英国国立公文書館の所蔵資料より、第二次大戦後の難民問題に関する官民双方の資料を収録するものです。前者からはヘンリクス文書集を、そして後者からは難民問題に関係する外務省・陸軍省・内務省文書を収録しています。ウィーナーライブラリーはユダヤ人難民に関する文書、内務省、外務省、陸軍省はユダヤ人を含む様々な国民・人種の難民に関する文書です。
ウィーナーライブラリーの所蔵文書はホロコーストに関するマイクロフィルム版文書集『ホロコースト証言録(Testaments to Holocaust)』の「第3集:ヘンリクス文書集(Series 3: Henriques Archive)」を電子化したものです。ヘンリクスとはローズ・ヘンリクス(Rose Henriques)のことで、ユダヤ人を救援する目的で第二次大戦中に設立された団体である海外ユダヤ人救援委員会(Jewish Committee for Relied Abroad)のドイツ部門長を務めた人物で、第二次大戦直後はドイツの英国占領地域でユダヤ人の救援活動に携わりました。
第二次大戦終結後、敗戦国ドイツは英米仏ソ4ヶ国の占領地域に分断され、軍政が敷かれました。このうち、英国の占領地域はシュレスヴィッヒ・ホルシュタイン、ノルトライン・ヴェストファーレン、ニーダーザクセン、ハンブルク市をカバーしました。強制労働、強制収容所、捕虜、国外追放等の理由で戦時中に強制移住させられた人々は、終戦時のドイツ全体で1,200万人を数え、英国占領地域だけでも200万人に達していました。これらの強制的に移住させられた人々の苦難は終戦直後も続きました。
難民問題に直面した連合国政府や非政府団体は難民に住居と食糧の提供を行ないました。難民を故郷に送還する計画が立案されたものの、多くの難民は故郷に戻ることができないか、あるいは戻ることを拒みました。帰国すれば銃殺か収容所送りにされる恐れのあったソ連出身の難民、母国が共産党政権の統治下に置かれたポーランド人や東欧出身のユダヤ人等、母国送還を拒む難民が多くいました。パレスチナへの移民を希望するユダヤ人も多かったものの、当時パレスチナを委任統治していた英国政府はユダヤ人のパレスチナ移民に反対の政策を取っていたため、難民収容所に止まることを余儀なくされました。ホロコーストを生き延びたユダヤ人の多くは皮肉なことに、ホロコーストの加害者であるドイツの地に設置された難民キャンプで身を守ることしかできない状況に置かれました。戦争直後の時期にはナチスの戦争犯罪人と同じ施設に収容されたユダヤ人難民もいました。さらにドイツ系ユダヤ人難民の場合は「敵国難民」として扱われ、敵国との交流を禁止する連合国の政策の下で他の難民との交流が著しく制限されました。
このような状況にあって、ユダヤ人の難民収容所は独自のコミュニティを形成しました。学校やシナゴーグや各種コミュニティ施設が建設され、イディッシュ語やヘブライ語が話されました。難民同士が結ばれることも多く、難民収容所は当時のヨーロッパの中でも最高レベルの出生率を記録しました。強制収容所が置かれたブッフェンヴァルトで後のイスラエルの集団農場キブツを先取りする社会実験も行われました。
ヨーロッパの難民問題をめぐっては1946年に国際難民機関が創設されますが、戦後の混乱と各国間の利害対立により解決は阻まれ、1951年の難民の地位に関する条約の国連採択と国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)の設立によって、難民問題に対する国際的な制度的枠組みが構築されることになります。
*収録文献リストをこちらからご覧いただけます。
(一部のマイクロ版タイトル:Testaments to the Holocaust — Series 3: Henriques Archive)
さらに詳しく
関連分野
- ヨーロッパ研究
- ユダヤ・ホロコースト研究
- 政治学・外交研究
- 20世紀研究
- 第二次世界大戦